・東南アジアで働きたいけど、必要な英語力は?
・仕事でどんな英語力が必要になるの?
・どんな時に英語が必要になるの?
といった疑問にお答えしていきたい。
今回はその4回目(最終回)だ。
小生は大手小売業イオンの駐在員として香港、マレーシア、ベトナム、ミャンマーにトータルで12年間滞在。
各国で商品部や新規合弁事業の管理担当を歴任。
現在は独立し、ミャンマーの最大都市ヤンゴンに居を構え、新規事業のスタートを準備中。
東南アジアで必要な英語力は?
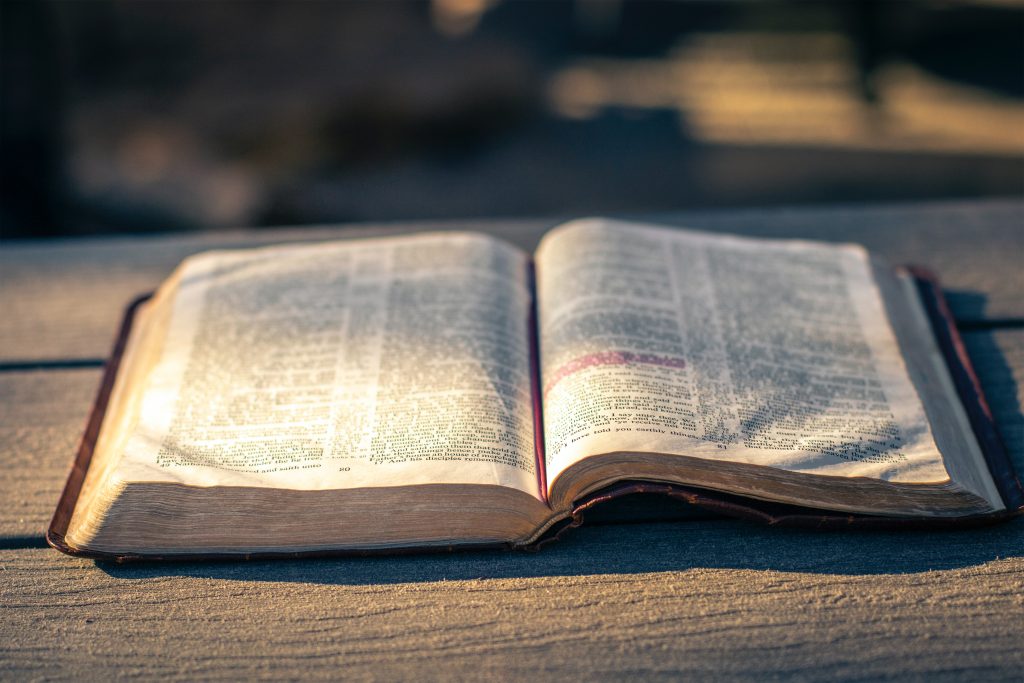
第2外国語として英語を話すベトナムやインドネシア、ミャンマーなど東南アジアで必要な英語力について、基礎的な土台は中学生、高校のレベルで十分と考える。
また、基本的な英会話のフレーズをシチュエーション別に暗記すれば、あとは場数を踏み、実践あるのみである。
それに加えて、グーグル翻訳やVoice Tra(NICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)が提供する音声翻訳アプリ)等の無料アプリを使えば、ほとんど困ることはないと思われる。
※Voice Tra(NICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)が提供する音声翻訳アプリ)は、本当に優れた、便利な音声翻訳アプリである。
前回まで
- 英文契約書
- 英語でのemailのやり取り
- ネイティブスピーカーとの商談
の3項目についてみてきた。
この3つは東南アジアのみならず、海外で仕事をする上で必ず克服しなければならない英d語の壁である。
特に1、2番については、渡航前には推薦書籍で学習することをお勧めする。
お薦めの英語学習方法は?

さて、シリーズ最終回は海外生活における「英語の学習方法」についてだ。
英語の教育に携わっている方、英語の専門家の方からお叱りを受けるのを覚悟で書くと
今まで述べてきた英文の「e-mail」「契約書」を除けば
東南アジアにおいて英語で間違えて伝えて、文脈やニュアンスなどに誤解が生じても、その後、訂正すれば問題はならないことが多い。
少なくとも私の経験からはそうだ。
※誤解されてはいけないので補足すると、私はすべての商談・ミーティングでベストを尽くしたし、できるだけ手寧に対応した。
→すでに触れたように欧米人との商談ではそうはいかないことも多いので要注意。
但し、金額や面積など数字は間違うと、後々問題になることがあるので慎重に伝えたい。
英語を第一言語としないアジア人同士のコミュニーケーションでは
自分の英語の理解 60%
相手の英語の理解 60%
であれば、60%×60%で3割程度しか相互に理解していないとの指摘がある。
さすればどうすれば良いのか?
毎回通訳を入れるのか?
はたまた、頭にはちまきを巻いて、現地のベトナム語やミャンマー語を取得するのか?
前者は立場や自分が所属している組織の予算事情というものがある。
後者は自分の能力と時間と相談しなければならない。
一番良いのは、合わせ技で
基本的には英語で説明し、大切なポイントは通訳を入れることが一番確実だ。
というのも、やはり英語であっても自分の言葉で伝えることが大切で、すべて通訳介しているようでは相手からの信頼は得られない。
しかし、
東南アジアを含む海外では公私ともに非常に忙しい。
とても、帰宅後、部屋にこもって英語の勉強はしていられないのである。
東南アジアにおけるビジネスの肝
話は少しそれるが、東南アジアビジネスの肝は
- 人脈構築力: 東南アジア、特にミャンマーは企業の看板ではなく、個人対個人の信頼関係でビジネスを進めるため、強固な人脈作りは必須となる。
- 財務力: 海外に来ると日本では中間幹部クラスでも経営に携わらなくてはならない。日本で商品や営業、総務系の業務に携わっていた人も必ず資金繰りなど財務のコントロールを遂行しなければならない。
- マーケティング力: 会社の商品やサービスをマーケットに広め、幹部みずからお客さまを店や販売店に連れてこなければならない。
- 組織力(≒システム化構築能力): 組織を構築する能力。日本のようにCEOやCOOや各本部長、管理本部長がいる大きな組織の構築は最初は難しい。あなた自身が複数のポジション(時には社長である貴方一人で、新人のみを抱え、新組織を運営していかなくてはならない場合もある)を兼任しなければならない。その時は、会社運営を人とITで「システム化」しなければならいない。
※ココデ・グローバル株式会社 代表取締役の加藤将太氏によれば次世代起業における「システム化」は「自動化と結果の保証」とのこと。
今後、機会があれば触れていきたい。
おすすめの英語学習方法
話が英語学習からそれたが、東南アジアで働く駐在員や経営者は公私ともにとても忙しい。
そんな中、どのようにして英語力を高めていけば良いのか?
答えは、移動や仕事の合間の隙間時間の活用しかない。
海外に限らず日本でもそうだが、細切れの時間をつなぎ合わせて積み上げ、量をこなしていくしかないと思う。
1日単語を3個覚えても、1年であれば1000個になる。
また、TOEICの勉強も、日本で勉強するより、日々の業務で実践できるので、モチベーションを維持するのが簡単だ。
私の周りにも、隙間時間を活用して、毎日15分から30分の英語学習を続け2年足らずでTOEIC450点から800点に改善し、現地の外資系企業に転職していった友人がいた。
「現地勤務での実用英語の実践」+「日々の隙間時間を使った英語学習」
でTOEICなどのスコアも200点以上のアップは十分可能である。
※TOEICにこだわるのではないが、私の経験からもTOEICのスコアが海外では一番通用する物差しとなる。
そんな中、私が推薦したい「英語学習方法」は次の2つで、隙間時間を利用して学習できるとともに、提供者(会社)も高い信頼がおけるものである。
リクルートが運営する英語学習サービス「スタディサプリENGLISH」『TOEIC(R)対策コース』

リース後たった2ヶ月で、250点スコアアップした人も!
リクルートから誕生したTOEIC(R)対策のための本格的プログラムです。
今の生活スタイルを大きく変えることなく楽しく無理なく気軽に続けられます!
微妙に忘れがちな中学レベルの文法の見直しからハイスコア対策まで対応!
最短1回3分から!スキマ時間で本格TOEIC(R)対策をすぐ始められます。
★セールスポイント
・250点アップはじめ、続々とスコアアップ報告が届いております!
・スマホ・PCでTOEIC(R)対策すべてを完結
・TOEIC(R)満点を取り続けるスタディサプリ第一人者の関正生講師が
丸暗記のない、一生使える英語の「核」を伝授
・人気の関正生講師の5分解説動画を140本も収録。英語基礎からパート別の攻略法まで。
・本番に近い問題形式の「実戦問題集」は、PART1~PART7全てに対応
・TOEIC(R)テスト20回分相当の実戦形式問題・解説を収録
・中学レベルの学び直しからハイスコア対策まで対応
・中学校の基本英文法からやり直せる、講義動画と演習問題もあるので初級者も安心
・最短1回3分からのTOEIC対策
・全ての機能が7日間無料でお試し可能
・TOEIC対策コースをお申込み頂くと、「日常英会話コース」も使い放題
(※「日常英会話コース」と「新日常英会話コース」は別サービスです)
私の周りでも、「TOEIC200点以上アップ」続出で
現地で起業したり、転職して自由な生活を手に入れる方もいる。
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BSQ05+6PQ0DU+3AQG+BXB8Z
![]()
【東大発】医学博士が教える英単語記憶術 ミリオン・ボキャメモリー

また、英語力≒英単語力である。
マルチに才能を発揮する元東京大学医学部附属病院医師の森田敏弘氏が開発した英単語記憶術である。
ここで推薦したいポイントは、この学習では、英単語に限らず、ビジネスで必要になる数多くの能力が同時に身につく点である。
シニアの方を含め、トータルな能力開発のため受講をお薦めする。
森田敏弘氏:
東京大学医学部卒 医学博士 元東京大学医学部附属病院医師
株式会社メディカルインフォメーションジャパン代表取締役
地方の新設校から初めて最難関の東京大学理科三類に合格。
心臓病の専門医として、東大病院の心臓カテーテル手術件数を10年間で50例から600例まで10倍以上に増やす。また次世代リハビリとして加圧トレーニングを東大病院に導入し、加圧ブームを起こした影の仕掛け人。
それまで公開していなかった独自の集中法を「東大ドクターが教える、やる気と集中力の高め方」で初めて公開し、話題を呼ぶ。
現在は医師としての活動以外にコンサルタントとしても活躍。
幼児からお年寄りまで、脳の使い方を変えて集中力を高める方法、能力を高める方法、認知症の予防法を指導している。
【特典】
- 365日年中無休で英単語・フレーズを暗記できるメルマガ The Daily English
- 森田先生の他の商品も最安値で購入できる権利プレゼント
- 勉強時間を大幅に削減できる1.5倍速プログラム
- 効果的に覚えた単語を復習できるミリボキャ単語帳
- スマホに入れて持ち運べるミリボキャ動画 ダウンロード版
- 120日間の返金保証を設けました。
※その他、アマゾンのKINDLE(毎月980円)に入会すると
森田先生の以下の書籍が無料で読める。
自己実現のため合わせてお薦めする。
■やるべきことがみるみる片づく東大ドクター流やる気と集中力の引き出す技術 Kindle版
森田 敏宏 (著) 出版社 : クロスメディア・パブリッシング(インプレス)発売日 : 2016/4/8
■「やる!」と決めたことが必ず続く24の法則 Kindle版
森田 敏宏 (著) 出版社 : クロスメディア・パブリッシング(インプレス); 発売日 : 2011/5/11
本日も最後までお読み頂きありがとうございました。
MASA
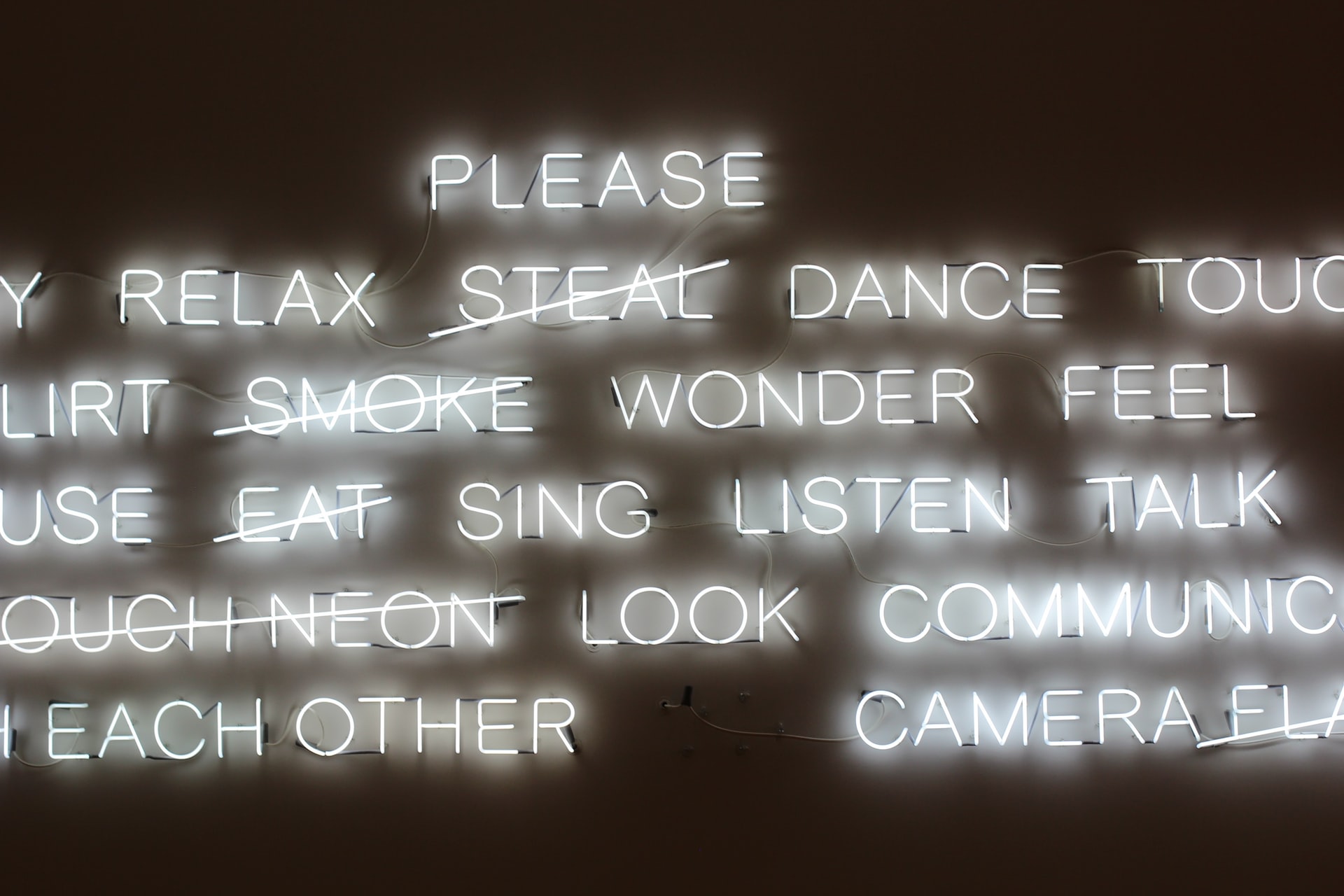


コメント